LAST-WG
LAbel Switch Technology Working Group
● 目標:
IETFにおいて、1997年3月から正式に標準化の検討が開始されているラベルスイッチ技術を用いた次世代インターネット技術に関する研究を、WIDEインターネットバックボーン上での運用を行いながら実証的に研究する。
WIDEプロジェクトにおいては、IETFでの標準化活動よりも早い時期から(1997年9月頃)技術検討を開始、1997年4月にLASTワーキンググループを設立した。
● 技術の背景:
TCP/IP技術の急速な普及と通信帯域の増加に伴い、パケット転送の高速化・大容量化および柔軟性(VPN機能やQoS/CoS機能など)高いパケット転送を実現することのできる新しいルータ技術の確立が急務である。ラベルスイッチ技術は、ラベル転送技術とレイヤ3ルーティングを統合する技術(図1)であり、任意のデータリンク(ATM,
Ethernet, Frame-Relay)および任意のレイヤ3技術(IPv4,IPv6)で適用することが可能である。
● 技術の概要:
定められたパケット流(粒度は任意)に対し固定長のラベルを対応させ、実際のパケット転送は、固定長のラベルを用いて行う(図1)。
Best-matchによるルーティングテーブル検索を、Exact_matchによる検索に変換することができる(高速化)とともに、受信パケットのIPアドレス解析が不要(新しいVPNサービス機能の実現)となる。
固定長のラベルとパケットフローのマッピングの確立を行うために、ルータ間で新しいプロトコル(LDP;
Label Distribution Protocol)を導入する必要がある。
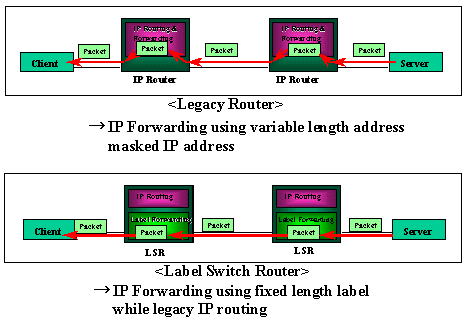
図1. ラベルスイッチングの動作原理
● 現状:
WIDEインターネットバックボーン(NTT殿、慶応大学殿との共同研究として)に、セルスイッチルータ技術(東芝)、タグスイッチ技術(Cisco
Systems)を1997年11月より順次設置し、ソフトウェアアップデートを適宜行いながら実運用を行っている(図2,3)。
タグスイッチ技術を NSPIXP2 において実験運用、セルスイッチルータ技術をWIDEインターネットバックボーンにおいて実験運用しながら、技術評価ならびに研究開発活動を進めている。
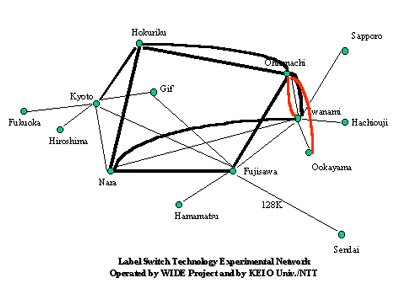
図2. WIDEインターネットバックボーン構成
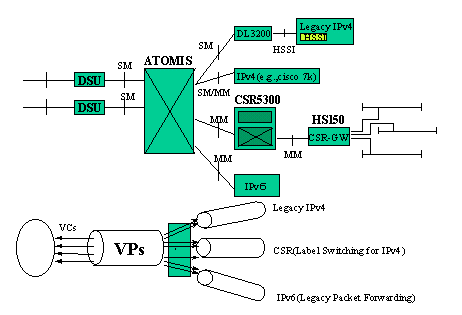
図3. コアNOC構成概要
● 今後の予定:
Differentiated ServiceアーキテクチャおよびRFC2309で議論されているActive
Queue制御技術(RED; Random Early Detection技術など)との統合化を行いながら、QoS
(Quality of Service) / CoS (Class of Service)への対応を進める。 さらに、IETF
MPLS-WG標準のラベルスイッチ制御プロトコルLDPへの対応を行う。
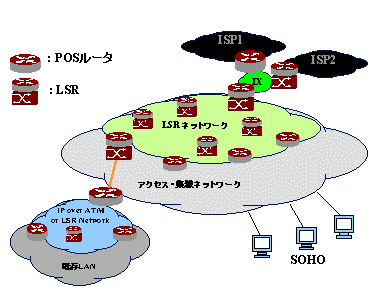
図4. ラベルスイッチルータ導入形態例
● 研究開発・製品動向:
Ipsilon社(現Nokia社) IP Switch(96年)、東芝CSR(97年)、cisco社タグスイッチ(98年)が独自プロトコルで製品化した。
現在、多数の研究組織及びベンダーにおいて研究開発および実装が進められている。
● 標準化活動:
1997年3月にMPLS-WG(Multi-Protocol Label Switching)が発足、Standard
Trackとして技術の標準化を進めている。 WIDEプロジェクトからも RFCやInternet-Draftの提案を行っている。
- RFC: RFC2098, RFC2129
- Internet-Draft : VCIDメカニズム
メーリングリスト: last-wg@wide.ad.jp
WG代表 : 東京大学 江崎浩(hiroshi@wide.ad.jp)
担当ボード: 慶應大学 中村修 (osamu@wide.ad.jp)
|